2019年4月に改正された労働基準法は、ワーク&ライフバランスの強化や健康的で働きやすい環境を推進させるため、従業員の年次有給休暇取得を企業に義務付けました。
この義務の履行を図るため、年次有給休暇管理簿の作成と保存も義務付けられています。
義務を怠ると罰金も科されるので注意が必要です。
この年次有給休暇管理簿について、特徴や作成方法から注意点まで解説していきます。
年次有給休暇管理簿とは
年次有給暇休管理簿とは、2019年4月から施行された労働基準法の改正により、全ての企業に作成と保存が義務付けられました。
これは、従業員一人ひとりの有給休暇の付与・取得状況を記録する書類であり、企業の労務管理における基本中の基本といえます。
有給休暇は、従業員の心身の健康やワークライフバランスを確保するうえで重要な制度です。
しかし、過去には「休暇の消化状況を把握していない」「働き手が権利を行使しづらい雰囲気がある」といった問題が多く存在しました。
そのため国は、企業が従業員に対して年5日の有給休暇を必ず取得させるよう義務化し、その実効性を担保するために管理簿を設けたのです。
労働基準法に関する記事はこちら
年次有給休暇の仕組みとは?
有給休暇は、労働基準法第39条で定められた労働者の権利です。
入社後6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日の有給休暇が付与されます。
以降、勤続年数に応じて付与日数は増加し、最長で年間20日が付与されます。
| 継続勤務年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 0.5年 | 10日 |
| 1.5年 | 11日 |
| 2.5年 | 12日 |
| 3.5年 | 14日 |
| 4.5年 | 16日 |
| 5.5年 | 18日 |
| 6.5年以上 | 20日 |
建設業界では、正社員だけでなく、契約社員やアルバイト、日雇いに近い勤務形態のスタッフも働いています。
この場合でも、一定の条件を満たせば有給休暇の対象となります。
つまり「正社員でないから対象外」という認識は誤りであり、全従業員に対して適切な付与と管理を行う必要があります。
年次有給休暇管理簿の定義
管理簿とは、従業員ごとに「基準日」「取得日数」「取得時季」を記録した書類を指します。
労働基準法施行規則第24条の7において作成義務が明記されており、様式自体は自由ですが必須記載事項を漏れなく記録しなければなりません。
例えば、現場監督Aさんの基準日が4月1日であれば、その日を起点として付与日数・取得日数を記載し、実際に休暇を取った日を管理簿に残します。
これにより、会社は「Aさんが年5日以上取得したかどうか」を確認でき、労働基準監督署の調査にも対応できます。
年次有給休暇管理簿の記載項目
年次有給休暇管理簿には、法律で必ず記載しなければならない項目があります。
また、実務上の管理をスムーズに行うために追加で記録しておくと便利な情報もあります。
ここでは、法令で義務付けられた必須事項と、現場運用で役立つ項目を整理して解説します。
必須記載事項
労働基準法施行規則第24条の7では、管理簿に記載すべき3つの事項が明記されています。
これらを欠くと、監督署の調査で指摘を受ける可能性があるため、必ず押さえておきましょう。
- 基準日(付与日)
従業員に有給休暇が付与される起算日を指します。
例:入社日が4月1日なら、その半年後の10月1日が基準日。 - 取得日数
基準日以降に従業員が実際に取得した日数を記録します。
年5日の取得義務があるため、この確認が最も重要です。 - 取得時季(取得した日)
いつ休暇を取ったのかを日付単位で残します。
取得実績が曖昧だと「休暇を与えていない」と見なされるリスクがあります。
その他の実務的に必要な情報
必須事項以外にも、日常的な管理をスムーズにするために記録しておくべき情報があります。
特に従業員数が多い建設業では、追加情報があることで確認の手間を大きく減らせます。
- 従業員氏名と所属部署(現場ごとの管理がしやすくなる)
- 雇用形態(正社員、契約社員、アルバイトなど)
- 残日数(付与日数から取得日数を引いた残り)
- 時間単位有休の取得記録(導入している場合)
例として、現場監督は「4月に2日取得」、事務スタッフは「午前休を2回取得」という具合に、分単位の休暇を管理簿に加えておくとトラブル防止につながります。
記入例
管理簿の形式は自由ですが、厚生労働省が提示しているサンプル様式を参考にするのが安心です。
Excelや紙で管理する場合でも、以下のような表形式が一般的です。
| 氏名 | 基準日 | 付与日数 | 取得日数 | 取得時季 | 残日数 | 雇用形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田太郎 | 2025/4/1 | 10日 | 3日 | 5/10、6/20、8/5 | 7日 | 正社員 |
| 佐藤花子 | 2025/4/1 | 10日 | 5日 | 4/15、5/2、7/18、8/30、9/5 | 5日 | アルバイト |
このように表形式で記録しておくと、基準日ごとに残日数をすぐに確認でき、監督署からの提示要求にも対応しやすくなります。
建設業ならではの注意点
建設業は現場単位で雇用管理が分かれやすく、管理簿が分散するケースがよくあります。
「本社と現場の記録が食い違う」「退職者の管理簿が残っていない」といったトラブルも少なくありません。
そのため、管理簿は本社が一元的に保管し、現場から申請を受けたら即時に反映する仕組みを整えることが重要です。
クラウド勤怠システムを導入すれば、現場監督がスマートフォンから申請した内容を本社が同時に確認できるため、二重管理のリスクを防げます。
休暇届・有給休暇管理表に関する記事はこちら
年次有給休暇管理簿の作成方法
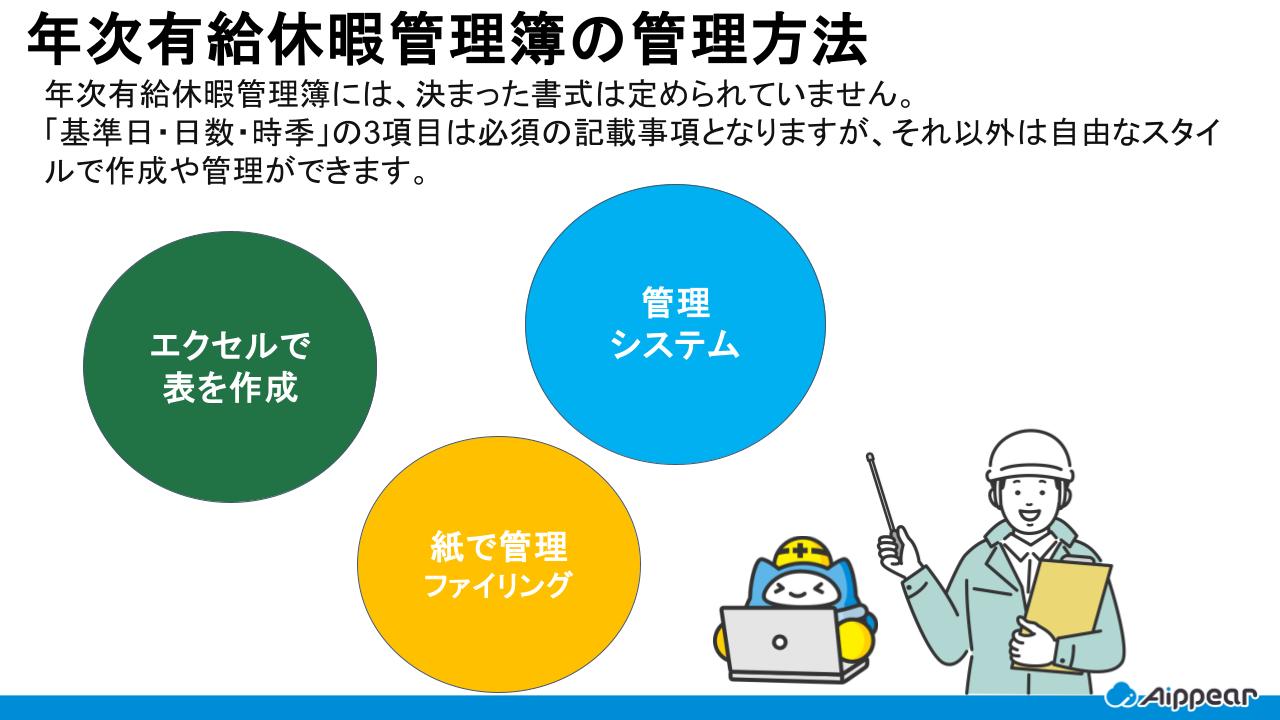
年次有給休暇管理簿は、法令で作成が義務付けられているため、必ず整備しなければなりません。
しかし、作成方法については「紙で手書き」「Excel」「システム導入」といった複数の方法が存在します。
それぞれにメリットとデメリットがあるため、自社の規模や現場環境に合わせて選択することが重要です。
方法①:手書きで作成
もっともシンプルなのが、紙の様式を利用して手書きで作成する方法です。
厚生労働省が公開しているテンプレートを印刷し、従業員ごとに管理簿を作成して保管します。
メリット
- 導入コストがかからない
- 紙の書類としてすぐに監督署へ提示できる
デメリット
- 記入ミスが発生しやすい
- 付与日数や残日数を手計算する必要がある
- 現場が複数ある場合、情報が分散して集計が困難
建設業の小規模な工務店や職人グループでは、まだ手書きで管理しているケースが多く見られます。
ただし、人数が10名を超えると記録の更新や確認に手間がかかり、労務担当者の負担が増大する点に注意が必要です。
方法②:Excelで作成
次に多いのが、Excelを使った管理方法です。
厚労省や民間サイトで無料のテンプレートが配布されており、それをベースに必要に応じてカスタマイズして運用します。
メリット
- 無料で始められる
- 自動計算式を入れることで残日数の管理が容易
- 紙に比べて修正がしやすい
デメリット
- ファイルが担当者のパソコンに依存しやすい
- 複数拠点で同時に更新できない
- バックアップを取らないと紛失リスクがある
建設業では、現場事務所と本社が分かれているケースが多く、Excelファイルをメールでやり取りしている企業もあります。
しかし、最新版のファイルがどれか分からなくなる、集計に時間がかかるといったトラブルはよく起こります。
そのため、ファイル共有クラウド(例:OneDriveやGoogleドライブ)を組み合わせて運用することが推奨されます。
方法③:勤怠管理システムで作成
より効率的かつ正確に管理できるのが、勤怠管理システムを利用する方法です。
クラウド型システムであれば、従業員の勤怠データから自動的に有給休暇の付与や残数計算を行い、管理簿として出力することが可能です。
メリット
- 基準日の自動設定や残日数の自動計算が可能
- 多拠点・多現場からリアルタイムで申請・承認できる
- 労働者名簿や賃金台帳と連携しやすい
- 法改正や制度変更にシステム側が対応してくれる
デメリット
- 導入コストがかかる
- 社員への操作教育が必要
建設業においては「現場監督がスマホから有休申請を行い、本社が自動で管理簿を更新する」といった運用が可能になります。
これにより、紙やExcelで生じやすい転記ミスや二重管理を防ぐことができ、監督署からの調査対応もスムーズに行えます。
作成方法の比較表
以下に、各方法を比較できる表を示します。
| 方法 | メリット | デメリット | 建設業での適性 |
|---|---|---|---|
| 手書き | コストゼロ、すぐ開始できる | ミスが多い、集計が大変 | 従業員10名以下の小規模向け |
| Excel | 無料テンプレ活用、計算が容易 | ファイル管理が煩雑 | 事務員が常駐している中小企業向け |
| 勤怠管理システム | 自動計算、リアルタイム共有 | 導入費用、教育が必要 | 現場が複数ある中堅〜大規模企業向け |
建設業ならではの工夫
建設業では、繁忙期と閑散期の差が大きく、有給休暇の取得が集中する時期が生じがちです。
そのため、管理簿を作成する際には以下の工夫が有効です。
- 基準日を年度初めに統一し、全社員を同じサイクルで管理する
- 繁忙期前に休暇計画を立て、管理簿に記入しておく
- 現場単位で取得状況を可視化し、特定の現場に負担が偏らないように調整する
このような工夫を取り入れることで、労務リスクを避けながら効率的に休暇管理が可能となります。
年次有給休暇管理簿の保存期間と罰則
年次有給休暇管理簿は、一度作成したらそれで終わりではありません。
法律上、一定期間保存しなければならず、保存義務を怠ると企業に不利益が生じる可能性があります。
ここでは保存期間と罰則について整理します。
保存期間
労働基準法に基づき、年次有給休暇管理簿は「3年間」の保存が義務付けられています。
この3年間とは、各従業員の管理簿を作成した日から起算されるため、年度ごとに記録を更新した場合には、その年度分を基準にカウントします。
例えば、2025年4月1日付で管理簿を作成した場合は、2028年3月31日まで保存しなければなりません。
紙媒体でも電子データでも問題ありませんが、建設業では「現場ごとに紙で管理し、本社に送付している」というケースも多いため、紛失のリスクに注意が必要です。
保存形式の工夫としては以下が挙げられます。
- 紙で保存する場合:専用ファイルやキャビネットに年度ごとに分類
- Excelで保存する場合:クラウドストレージに年度別フォルダを作成
- システムで保存する場合:自動で保存期間を管理する機能を活用
罰則規定
保存義務を怠った場合、労働基準監督署から行政指導を受ける可能性があります。
特に「管理簿を作成していない」「保存していない」ことが発覚すると、労基法違反として指摘を受けます。
また、有給休暇の年5日取得義務を守らなかった場合は「30万円以下の罰金」の対象になることが法律で定められています。
これは従業員の取得状況を正しく管理していなかった場合にも該当するため、管理簿の不備は企業にとって大きなリスクとなります。
保存と罰則のまとめ表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保存期間 | 3年間(紙・電子どちらでも可) |
| 保存方法 | 紙ファイル、Excel(クラウド保存)、システムによる自動管理 |
| 罰則 | 管理簿未作成・未保存は行政指導、有給年5日未取得は30万円以下の罰金 |
| 建設業の注意点 | 現場ごとに分散しやすく紛失リスク大、退職者分も必ず保存 |
管理簿の保存期間を守ることは、法令遵守の基本であると同時に、労務リスクを最小限に抑える手段です。
「3年間」というルールを徹底し、現場と本社の管理を統一することで、突然の監督署調査にも安心して対応できるようになります。
業務効率化・一元管理のシステムについてはこちら
年次有給休暇管理簿を効率的に管理するポイント
年次有給休暇管理簿は、ただ作成するだけではなく、効率的に管理してこそ意味があります。
特に建設業のように従業員が多拠点・多現場で働く業種では、管理の手間やミスを防ぐ工夫が欠かせません。
ここでは、管理精度を高めつつ労務担当者の負担を減らすためのポイントを解説します。
基準日の統一
有給休暇の基準日は、従業員ごとに入社日を起点にするのが原則です。
しかしこの方法だと、従業員一人ひとりの付与日がバラバラになり、管理簿の更新作業が複雑になります。
そこで有効なのが「基準日の統一」です。
例えば、年度初めや年初に一括付与することで、全従業員の管理を同じサイクルで行えます。
- 方法① 年度初めに統一
学校や官公庁と同じ4月を基準日とすると、繁忙期に備えて管理がしやすくなる。 - 方法② 月初に統一
毎月1日を基準日とすることで、現場単位で人員調整を行いやすくなる。
建設業では繁忙期(例:年度末や大型案件の前)に人員が集中しやすいため、基準日の統一は業務効率化に直結します。
労働者名簿・賃金台帳との一体管理
年次有給休暇管理簿は単独で運用するよりも、労働者名簿や賃金台帳とあわせて管理すると効率的です。
従業員の基本情報、給与計算、有給休暇残日数を一元化することで、入力作業の重複を防げます。
例えば、従業員の退職処理を行う際に、有給残日数が自動的に参照できれば「退職前に消化が必要かどうか」をすぐに判断できます。
これは建設業のように人員の出入りが多い業界では特に役立ちます。
システム活用によるメリット
勤怠管理システムを導入すれば、年次有給休暇管理簿の作成から保存まで自動化できます。
クラウド型であれば現場と本社が同時にデータを確認できるため、管理の遅れや二重入力のリスクを解消できます。
主なメリット
- 基準日の自動設定
- 残日数の自動計算
- 取得状況のリアルタイム把握
- 労基署調査にそのまま提出可能なデータ出力
実際に中堅規模の建設会社で導入したケースでは「Excel管理に比べて月10時間以上の労務担当者の工数削減」「有給残数の誤管理ゼロ」を実現しています。
現場ごとの見える化と調整
建設業では現場単位で人員配置を行うため、有給休暇の取得が一部の現場に偏ると業務に支障が出ます。
そのため、管理簿を用いて「どの現場に休暇取得者が集中しているか」を可視化し、計画的に調整することが重要です。
例えば、同じ時期に同一現場で複数人が休む場合は、事前に別の現場から応援要員を手配するなど、管理簿を活用した人員計画が有効です。
年次有給休暇管理簿に関するよくある質問(FAQ)
- 管理簿の様式は決まっていますか?
-
様式は法律で指定されていません。
厚生労働省がサンプル様式を公開していますが、必須記載事項である「基準日」「取得日数」「取得時季」が記載されていれば、紙でもExcelでもシステム出力でも問題ありません。
実務では、Excelやシステムをベースに、自社の雇用形態や現場単位の管理方法に合わせてカスタマイズするのが一般的です。 - パート・アルバイトも対象ですか?
-
はい、対象です。
労働基準法では、所定の条件を満たすすべての労働者に有給休暇を付与することを義務付けています。
そのため、パートやアルバイトであっても、勤務日数に応じて比例付与が必要になります。
建設業においては、短時間勤務の現場スタッフも対象になるため、管理簿で正しく記録しておく必要があります。 - Excel管理とシステム管理はどちらが良いですか?
-
小規模企業で従業員数が少ない場合はExcelでも十分対応可能です。
ただし、複数拠点を持つ建設会社や従業員数が多い場合には、クラウド型勤怠システムの導入が推奨されます。
理由は、Excelではファイルの共有や更新が煩雑になりやすく、最新版の確認に手間がかかるためです。
一方、システムはリアルタイムで更新でき、労基署調査にもそのまま出力して対応できる利点があります。 - 取得義務の「年5日」はどう確認しますか?
-
管理簿に記載した「取得日数」と「取得日」を確認することで判断できます。
基準日から1年間の間に5日以上取得していない従業員がいれば、企業側は計画的付与や時季指定を行う必要があります。
この確認ができるのは管理簿しかないため、記録を正確に残しておくことが不可欠です。 - 建設業特有の「突発休み」はどう扱いますか?
-
天候不良や急な現場停止などで休みになる場合は、原則として有給休暇には該当しません。
会社都合での休業であれば「休業手当」の対象となるケースが多いため、管理簿には記載せず、別途勤怠管理で対応します。
一方で、従業員自身が「有給を使いたい」と申請した場合には、管理簿に取得日として記録する必要があります。
建築・リフォームの工事管理なら『管理システム アイピア』
アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。
さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。
アイピアはここが便利!6つのポイント
まとめ
今回の記事では、年次有給休暇管理簿について詳しく解説してきました。
年次有給休暇管理簿とは、労働基準法の改正に伴い企業に作成と3年間の保存が義務付けられる書類です。
罰金の負担を避けるためにも、法律のルールにもとづき、年次有給休暇管理簿を作成し、基準日・日数・時季を必ず記載して管理しなくてはなりません。
エクセルなどで作成、管理することもできますが、手間を省きデータを確実に管理、保存していくためにも、年次有給休暇管理簿を効率化する勤怠管理システムの導入がおすすめです。
業務改善を進めるポイントはこちら
- 業務改善の効果的な進め方!ポイントやフレームワークを徹底解説
- 業務改善を効率的に進めるポイントとは?
- 施工管理の効率化手法とは?メリットとポイントも解説!
- 【超初級】業務改善報告書の基本的な書き方とは?テンプレート例つき
- 【最新版】業務改善助成金とは?簡単な申請方法から注意点まで
- 業務効率化とは?具体策と進める際のポイントを解説
- 業務効率化とは?具体策と進める際のポイントを解説
ツールを使った業務改善ならこちら
36協定に関する記事はこちら
“社内のデータを一元管理”工務店・リフォーム会社が選ぶ!










