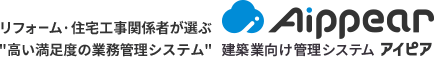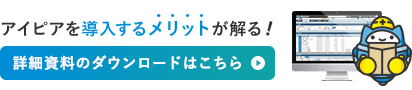時間削減・利益UP・情報共有ができる
建築業の見積業務がラクになる!一元管理システムならアイピア
アイピアは建築業に特化したシステムであり、見積管理をはじめ工事に関するあらゆる情報を一括で管理できます。さらにアイピアはクラウドシステム。外出先からでもデータを確認できます。
下請け企業で働いていると、元請けから見積書に法定福利費を含めるように指示された経験を持つ方もいるのではないでしょうか。
現在、国土交通省は建設業における社会保険の加入対策に力を入れています。
社会保険に加入している企業だけではなく、建設業で見積りを提出する際は、個人経営の事務所、一人親方であっても、必要な社会保険料を確保し、内訳を記載しなければなりません。
建設業では、この法定福利費を見積書に含める事があります。
本記事では、法定福利費を見積書に含める理由と、その場合の書き方について解説していきます。
目次
法定福利費とは
法定福利費とは、企業が支出する福利厚生費のうち、法令・政令によって会社に費用の負担が義務づけられているものです。
企業が負担する社会保険料や労働保険料が、法定福利費の対象です。
法定外福利費との違い
従業員のために企業が負担する給与外の費用を、福利厚生費といいます。
福利厚生費には、「法定福利費」と「法定外福利費」があり、両者は異なる費用です。
法定福利費と違い、法定外福利費には法的な義務付けがありません。
法定外福利費には、次のようなものが含まれます。
- 通勤手当
- 社宅の賃料
- 健康診断費用
- 新年会や忘年会等の費用
仕訳の際は、法定福利費と福利厚生費を分けて記帳するようにしましょう。
法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(記入例あり)
建設業者が工事を請け負う際、元請業者に提出する見積書には法定福利費を明記する必要があります。
ただし、見積書に記載する法定福利費は、事業主が負担する部分のみです。
もしそれ以外の法定福利費を含める場合は、その旨を明記し、該当する金額を労務費から差し引く必要があります。
ここでは、法定福利費の記載方法を分かりやすくするために、具体的な見積書内訳の例をご紹介します。
●見積書の例

※事業主負担分の法定福利費は、別に計上するので、経費から除いておきます。
●法定福利費(事業主負担分)

また、法定福利費を含む見積書は、下記の手順で作成します。
- 労務費を計算する
- 労務費から法定福利費を計算する
- 法定福利費を見積書に明記する
ポイントは、法定福利費を含めて消費税を計算することです。
それでは、具体的に解説していきます。
STEP1 労務費を計算する
労務費の算出方法は、企業ごとに異なる可能性があります。
しかし、一般的には下記のように算出します。
労務費 = 必要な人工数 × 平均の日額賃金
CHECK!
「リフォームキッチン工事」の場合
- 必要な人工数:20人工
- 平均の日額賃金:15,000円
労務費 = 300,000 = 20 × 15,000
つまり、この場合は300,000円が労務費となります。
CHECK!
厚生労働省「建築事業の労務費率」を活用する場合
厚生労働省で決められている労務比率を活用し、それを工事費に掛けることで労務費を計算する方法もあります。
本体工事が1,000,000円の場合、建築事業の労務費率23%を活用すると次のように労務費を求められます。
労務費 = 230,000 = 1,000,000 × 23%
つまり、この場合の労務費は230,000円です。
STEP2 労務費から法定福利費を計算する
見積書に記載する法定福利費は、労務費に社会保険料率をかけて計算します。
- 健康保険料
- 介護保険料
- 厚生年金保険料(子ども・子育て拠出金含む)
- 雇用保険料
のうち、事業主負担分のみを見積書に記載します。
事業主負担分の割合は下記のようになります。
- 健康保険:折半
- 介護保険料:折半
- 厚生年金保険料:折半
- 雇用保険料:業種によって割合が変わります
- こども・子育て拠出金:全額負担
健康保険、介護保険料、厚生年金保険料の保険料率は、全国健康保険協会(協会けんぽ)が公開しています。
保険料率は、都道府県ごとに異なり、年に数回改定されるため、見積書作成時の保険料率を確認する必要があります。
それでは、令和6年度の東京都の保険料率で計算してみます。
労務費が1,000,000円の場合の法定福利費は下記のようになります。
STEP3 法定福利費を見積書に明記する
法定福利費を算出したら、以下の図のように見積書に記載してください。
図の通り、法定福利費を記載する際は、工事費と分けて明確に記載してください。
また、労務費率や保険料率を基に法定福利費を算出している場合は、工事価格、労務比率、保険料率も併せて記載する必要があります。
法定福利費も消費税の対象となる点に注意が必要です。
見積システムに関する記事はこちら
法定福利費の種類
法定福利費の概要を確認しました。
法定福利費の対象となる保険は、次の6種類です。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 子ども・子育て拠出金
- 雇用保険
- 労災保険
それぞれ詳しくみていきましょう。
健康保険
健康保険は、従業員とその家族(被保険者)の医療費の一部が負担される制度です。
従業員が正社員の場合は、原則的に加入義務があります。
また、従業員がパート・アルバイトの場合でも、常勤の場合は加入義務があります。
厚生年金保険
厚生年金保険は、会社に勤務する従業員が加入する公的年金を指します。
正社員のみならず、一定の労働時間以上働くことで、パートやアルバイトでも厚生年金保険の対象になることがあります。
また、一定の要件に該当すれば、扶養配偶者も給付対象となります。
一方、自営業・短時間労働者・無職の場合は、厚生年金保険の対象になりません。
この場合、国民年金へ加入する必要があります。
介護保険
老化による病気・けが・障がいなど、介護を必要する人々の費用を一部負担するのが、介護保険です。
40歳以上の従業員は被保険者となり、保険料を支払う義務があります。
子ども・子育て拠出金
子ども・子育て拠出金は、国や自治体が設ける子育て支援のための拠出金です。
企業が全額負担することになっているため、従業員の負担はありません。
雇用保険
雇用保険は、労働者が失業や休業した際、再就職や失業時の生活の安定のため給付を受けることができる制度です。
規模・業種に関わらず、全ての事業で適用されます。
そのため、該当の事業所に雇用される従業員は、被保険者となります。
労災保険
労災保険は、業務上または通勤の際に労働者が病気やケガを負った場合、または死亡した場合、労働者やその遺族が保険給付を受けることができる制度です。
正社員だけでなく、パートやアルバイトも受給対象です。
建設業の制度に関する記事はこちら
見積書に法定福利費を明示する理由
建設業では、就労環境の改善による持続的発展に必要な人材の確保を図るため、「社会保険等未加入の対策」に取り組んでいます。
社会保険等未加入対策をするには、企業が法定福利費を確保する必要があります。
平成25年9月には「社会保険未加入対策推進協議会」により、下請け企業からの見積書に法定福利費を記載し、工事価格と合わせて提出する取り組みが開始されました。
この取り組みにより、現在建設業では見積書に法定福利費を記載することが義務付けられています。
建設業の課題に関する記事はこちら
見積書を提出する際の注意点
見積書を提出する際には、元請業者と下請業者の双方がそれぞれに注意すべきポイントがあります。
見積書は工事契約の基盤となる重要な書類ですので、内容に誤りや抜けがないよう、慎重に作成・提出することが求められます。
ここでは、下請け業者と元請け業者それぞれの注意点について紹介します。
元請業者
工事を発注する際には、下請け業者の法定福利費を含めた金額で見積書を作成するようにしなければなりません。
そのため、元請け業者は、下請け企業から受け取った見積書を確認し、法定福利費が正確に記載されているかどうかを確認する必要があります。
中には、従業員が保険に加入していないために法定福利費を記載できない下請け企業も存在するため、注意が必要です。
こうした下請け企業と契約した場合、万が一事故などが発生すると、自社の評判にも影響を及ぼす可能性があります。
元請け業者は見積書の確認を徹底し、下請け業者の保険加入状況にも留意することが重要です。
下請業者
下請け業者は、工事の見積書を作成する際に法定福利費を正確に記載する義務があります。
中には、計算の手間を省くために「請負額」として大まかな金額を記載しようとする業者もいますが、法定福利費は必ず正確に計算された金額を記載しなければなりません。
元請け企業は、見積書に法定福利費が正しく記載されているかを確認しています。
もし適当に扱うと信用を失い、仕事を依頼されなくなる可能性もあるでしょう。
そのため、法定福利費の内容を正しく理解し、正確に記載することが大切です。
法定福利費を内訳明示した見積書のよくある質問
ここでは、法定福利費を内訳明示した見積書についてよく寄せられる質問を紹介します。
法定福利費を明確に記載した見積書について理解を深めるために、ぜひご参考ください。
Q. 法定福利費を内訳明示した見積書を作成する際には、所属する専門工事業団体の見積書に従って法定福利費を算出する必要がありますか?
A. 法定福利費の額は、各建設業者が自社の施工実績に基づいて算出するものであり、必ずしも専門工事業団体の標準見積書に従う必要はありません。専門工事業団体の見積書は、あくまで参考として使用するものです。
Q. 法定福利費を内訳明示した見積書を作成する際、専門工事業団体が作成した様式を使わなければいけないのでしょうか?
A. 法定福利費を内訳明示した見積書は、必要な法定福利費を確保することが目的です。そのため、内訳が明示されていれば、自社や注文者が指定した様式を使用しても問題ありません。専門工事業団体が作成した標準見積書は、あくまで参考として利用するものです。
Q. 法定福利費も消費税の対象となるのでしょうか?
A. 対象となります。
Q. 法定福利費を内訳明示した見積書の作成は、法律上の義務なのでしょうか?
A. 法定福利費の内訳明示は法律で義務付けられていませんが、元請企業がこれを無視して削減した場合、建設業法(第19条の3不当に低い請負代金の禁止)に違反する可能性があります。社会保険の加入促進のため、標準見積書の活用が推奨されており、その環境整備が進められています。
建設業の見積書を作成するなら『建設業向け管理システム アイピア』
建設業における見積書は、階層見積を作成する場合や工事に関する情報を記載する必要があるなど、他業種と比べて特殊です。
また、冒頭でも述べた通り、法定福利費の明示を推進する取り組みがなされていることから、見積書の作成はますます手間のかかる作業となります。
そこで、建設業の見積書でも簡単に作成できる『建築業向け管理システム アイピア』をご紹介します!

アイピアは、建築業向けの一元管理システムであり、見積書に必要な案件情報や見積・原価情報などを顧客に紐づけて管理できます。また、法定福利費の計算で必要な労務費も案件に紐づけて管理できるので、情報を探す手間が省けます。
さらに、アイピアは見積機能が充実しています。
アイピアで出来ること(一部)
- 多階層見積に対応しています(5段階まで)
- クラウドでどこからでも見積作成ができます
- 見積マスタ、過去の見積の再利用ができます
- 原価から粗利一括反映機能で見積価格を更新できます
- 金額の一括更新、値引き機能など計算機能が豊富です
- エクセルの情報をコピーで張り付けができます
- 基本的なエクセルの機能が使えます(並び替え、切り取り、張り付け、行コピー(Ctrl+C))
- 作成した見積書をエクセルでダウンロードができます
- 案件情報と紐づけて労務費を管理できます
まずは、体験デモで使用感を体感してみませんか?
今なら『最大450万円』の補助を受けられるチャンス!詳細はこちら
まとめ
社会保険の加入は任意ではなく法令上の義務です。
法定福利費を含めた見積書には、建設業における社会保険未加入対策を解決する重要な役割があります。
法定福利費の確保は怠らず、しっかりと理解したうえで見積書の作成をするようにしましょう。
見積の基礎知識に関する記事
- 建築・リフォーム業の見積書の書き方と見本(サンプル付き)
- 【建設業向け】見積書に法定福利費を含める理由と書き方を解説
- 【建築業向け】すぐに使える見積書 エクセルテンプレート(無料・登録不要)
- 見積書のメールに対する返信は?【例文あり】ポイントを徹底解説
リフォーム・工務店向け見積ソフト(システム)に関連する記事
- 建築見積ソフトおすすめ16選!建築業向けに選ぶポイントや特徴を解説!
- 見積システムのクラウドとインストール型の違いは?おすすめ13選
- 【工務店向け】見積管理システムで悩みを解消するポイントとは!
- 【リフォーム業向け】見積システム比較5選!選ぶポイントやメリットを紹介!
- 【建設業向け】見積書をアプリで簡単に作成!おすすめアプリ8選
工種別見積ソフト(システム)に関連する記事
"社内のデータを一元管理"工務店・リフォーム会社が選ぶ!