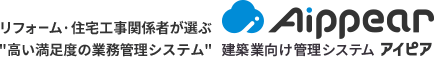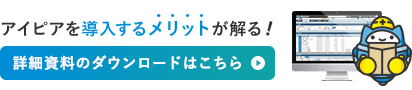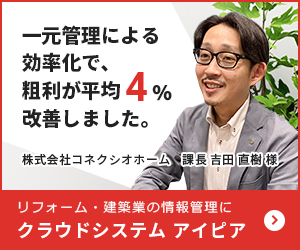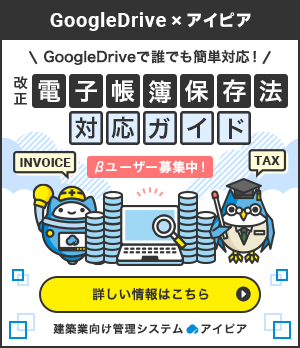造園工事業においても、建設業許可を得ることで仕事の幅が広がり、より高額な依頼案件を得ることが可能となります。
より大規模な公共工事を担いたい、より高額の工事を請け負って収益を伸ばしていきたいといった場合は、造園工事業で建設業許可を取得するのがおすすめです。
ここでは、造園工事の種類や内容と建設業許可を得るための要件を詳しく解説していきます。
造園工事とは

そもそも造園工事とは何なのでしょうか。
庭を造る工事のことですが、一般住宅の庭をはじめ、神社仏閣や公園などの庭を整備したり、緑地などを整備したり、広い面積で大規模な庭づくりをする工事です。
庭園を造るうえでは、さまざまな工事が必要となり、具体的には以下のような工事の種類に分けることができます。
造園工事の種類
造園工事の主な種類と、どのような工事を行うのか見ていきましょう。
植栽工事
植栽工事は庭木などを植える工事です。
一般住宅の玄関前にシンボルツリーを植えたり、庭に季節の木々を植えたりすることをはじめ、大きな庭園やゴルフ場に木を植えたり、地域の道路脇に街路樹を植えたり、公園の周囲に生け垣を造ることも植栽工事に該当します。
なお、植栽工事には、植生を復元するという建設工事も含めることができます。
地被工事
地被工事は、地面全体を植物で被う工事のことです。
たとえば、芝生を敷設することや和風庭園などに苔類などを一面に配する工事になります。
一般住宅のお庭に芝生を張る、公園やゴルフ場、スポーツ施設のグラウンドなどに芝生を敷き詰めるような依頼が挙げられます。
景石工事
庭園の景観を美しくする目的で庭石を配することや石垣など造成する工事のことです。
地ごしらえ工事
地ごしらえ工事とは、木を伐採した後や草刈りや芝刈りなどをした後、その廃棄物を収集して処分する作業です。
単なる廃棄物処理の作業ではなく、伐採した後や除草した後の表層土が流出するのを防ぐ目的やその後に植え替える苗木が丈夫に育つよう、養分の源を整える役割も果たしています。
公園設備工事
公園に滑り台やジャングルジム、ブランコやアスレチック設備などの特定の設備を設置する工事や花壇や噴水、休憩所などを設置、整備したり、公園に植栽を植えたりする工事のことです。
公園を整備するために必要な、さまざまな設備や施設などの設置を担う工事です。
広場工事
広場を整えるための工事になります。
芝生広場を造る、運動広場を造るなど、それぞれの目的に合わせた整備を担います。
園路工事
遠路工事は公園に遊歩道やサイクルイングロードを設けることや緑道などを整備する工事です。
水景工事
水景工事は水を利用した景観を作り上げる工事です。
噴水や池、人工の滝や水遊びをする人工の小川などを設置する工事やメンテナンス工事が該当します。
子どもたちが水遊びできる場所をはじめ、きれいな水の状態を保つために、ろ過施設や殺菌設備の施工も求められます。
屋上等緑化工事
ビルや商業施設、工場などの建築物の屋上や壁面、道路などを緑化する工事のことです。
特定の空間に生け垣や木を設ける工事や屋上庭園などを造る工事が該当します。
緑地育成工事
緑地育成工事とは、樹木や草花、芝生や苔類などの植物を育成するための工事で、土壌改良や支柱の設置などの作業も含まれます。
造園工事に関する記事はこちら
建設業の許可は必要?

建設業というと建物を建てるイメージが強いので、造園業とは結びつかないかもしれません。
ですが、軽微な建設工事を除き、造園工事を請け負うには建設業の許可を取得しておくほうが、仕事の幅が広がり、高額な工事を請け負うことが可能となります。
軽微な建設工事とは、たとえばシンボルツリーを1本植えるだけといった工事の内容で判断するのではありません。
工事代金の額で判断されます。
工事代金が消費税込みで500万円未満であれば、軽微な建設工事にとなります。
これに対して、工事代金が500万円以上になる場合には、請け負う工事が公共工事か民間工事かを問わず、造園工事業において建設業許可を取得しなければ、請け負うことができません。
一般建設業と特定建設業の違い
建設業の許可といっても、実は2種類あります。
一般建設業は発注者から直接依頼を受けて元請けとして工事を行う場合は、1件の発注あたりの工事代金の全額が6,000万円未満の場合か、全部または一部を下請けに出す場合の下請代金が4,000万円未満の場合、または下請けのみで営業を行う場合です。
一方、特定建設業は元請けとして請け負う、1件あたりの建築一式工事額が6,000万円以上か、全部または一部を下請けに出す場合の下請代金が4,000万円以上になる場合です。
大臣許可と知事許可の違い
許可を取得する申請先は、どこで営業を行うかで異なります。
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
一方、1つの都道府県のみで営業を行う場合には都道府県の知事許可でかまいません。
建設業の許可に関連する記事はこちら
造園工事業で建設業許可を取得する要件

造園工事業で建設業許可を取得するには、以下の要件を満たさなくてはなりません。
要件を満たすことを証明する資料の提出も求められます。
現時点の状況で要件を満たしていない場合は、要件を満たすように整備したり、必要な人材を採用したり、資格を取得するなどすることが必要です。
なお、造園工事業者において、外構工事やエクステリアの施工を担っているケースも少なくありません。
土間工事や建材メーカー製の外柵を設置する外構工事やエクステリア施工を大規模で高額の工事を担う場合は、造園工事業で建設業許可ではなく、別途とび土工コンクリート工事の建設業許可も取得する必要があるので注意しましょう。
経営業務の管理責任者の配置
経営業務の管理責任者として、一定の条件を満たす人材を配置することが必要です。
法人の場合は常勤役員のうち1人、個人事業主の場合は本人または支配人の1人が管理責任者の条件を満たさなくてはなりません。
経営業務の管理責任者の条件
以下のいずれかの条件を満たしていると、経営業務の管理責任者として認められる可能性が高いです。
造園工事業を営む会社で5年以上の役員経験があるか、造園工事業の個人事業主として5年以上経験を積んでいること、もしくは造園工事ではない建設業を営む会社で5年以上の役員経験があるか、造園工事業以外の建設業を個人事業主として5年以上経営していることです。
なお、植木の剪定や伐採、草刈り業務を担う、いわゆる植木屋さんをしていたとしても、造園工事や造園工事以外の建設業には該当しません。
そのため、植木屋さんとしての経験や実績は、造園工事の経営経験や実務経験の実績として認められないので注意しましょう。
専任技術者の配置
建設業の許可を取得するには、専任技術者を営業所ごとに常勤で置かなければなりません。
一般建設業の許可の場合
一般建設業の許可の場合に専任技術者として認められるのは、以下のいずれかの条件を満たす人です。
造園工事の実務経験が10年以上あるか、建築学、土木工学、都市工学、林学のいずれかの学科を卒業し、かつ、造園工事の実務経験がある人は専任技術者として認められます。
また、以下の国家資格等を有する方も、一般建設業の専任技術者として認められます。
一級造園施工管理技士、二級造園施工管理技士、技術士法の建設・総合技術監理(建設)、技術士法の建設(鋼構造及びコンクリート)、総合技術監理(鋼構造及びコンクリート)、技術士法の森林林業総合技術監理、技術士法の森林土木総合技術監理、職業能力開発促進法の造園技能士です。
なお、造園技能士二級の場合は3年以上の実務経験が必要になります。
特定建設業の許可の場合
特定建設業の許可を得るために専任技術者として認められるのは、下記の国家資格などを有する人です。
一級造園施工管理技士、技術士法の建設・総合技術監理(建設)、技術士法の建設(鋼構造及びコンクリート)、総合技術監理(鋼構造及びコンクリート)、技術士法の森林林業総合技術監理、技術士法の森林土木総合技術監理、そのほか、国土交通大臣が上記と同等以上の能力を有すると認めた人などです。
誠実性がある
誠実性と言われても、どう満たせば良いのかわかりにくいかもしれません。
建設業においては、大規模な工事が多いほか、相談や契約の段階から工事が完成するまでに数ヶ月から数年という長期に及ぶケースも少なくありません。
途中で事業を投げ出したり、不正な行為をして工事の品質を低下させたりするような行為があっては困ります。
そのため、誠実に業務を執り行える状態にあることが求められます。
たとえば、建築士法や宅地建物取引業法における不正な行為や不誠実な行為によって免許の取消処分を受けた場合やその処分の日から5年を経過していない場合は誠実性は認められません。
また、反社に該当するような人物が関わっているようなケースも誠実性は認められません。
財産的基礎を有している
誠実性の要件が求められる理由と同じで、建設業を行っていくうえでは完成まで長期に及ぶことが想定されます。
工事を請け負ってから完成させるまでの間に倒産して、工事が途中でできなくなっては困ります。
また、資金が十分でないことから、本来求められる品質の設備や資材を用いず、工事の内容が低品質になるのもNGです。
工事に携わる人材に十分な賃金を与えられない、適切な職場環境を与えられず、劣悪な状況で事故が起きる場合や死傷事故などが起きては大変です。
そのため、財産的基礎がしっかりしていることも、建設業の許可を得るための要件として求められます。
一般建設業の許可の場合
一般建設業の許可の財産的基礎の要件は、以下のいずれかを満たさなくてはなりません。
直前決算で自己資本額が500万円以上であるか、500万円以上の資金調達能力があることです。
特定建設業の許可の場合
特定建設業の許可を得たい場合には、以下のすべての条件を満たさないと、財産的基礎が認められません。
その条件とは、資本金額が2,000万円以上であること、自己資本額が4,000万円以上であること、欠損額が資本金の20%を超えないこと、流動比率が70%以上であることです。
欠格要件に該当しない
経営を担う重要人物が、欠格要件に該当しないことが必要です。
たとえば、法人の役員や支店長、個人事業主やその支配人が、成年被後見人、被保佐人、破産して復権を得ない者であると欠格要件に該当し、許可が得られません。
また、禁錮刑以上の刑に処せられた場合や刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者や、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者などは欠格要件に該当するので注意しましょう。
社会保険・雇用保険に加入している
建設業の許可を受けるレベルになれば、経営者1人では事業を運営することができず、通常、従業員を雇うことになります。
この場合に、健康保険や厚生年金保険などの社会保険および、雇用保険に加入して、しっかりと保険料を納めていないと、建設業の許可が得られません。
適用事業所としての条件に該当するすべての営業所において、社会保険の適用事業所の届出を提出していなくてはなりません。
まとめ
造園工事とは植栽工事や地被工事、景石工事や地ごしらえ工事、公園設備工事や広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事などの工事を行う業者を指します。
造園工事を営むうえで請け負う仕事の幅を広げ、より大規模で高額な工事を請け負いたいなら、建設業の許可を得ることがおすすめです。
一般建設業と特定建設業では請け負える工事金額に違いがあります。
大臣許可と知事許可の違いは複数の都道府県に営業所を設置するか、1つの都道府県のみで事業を行うかの違いです。
造園工事業で建設業許可を取得する要件として、経営業務の管理責任者や専任技術者を配置すること、誠実性があること、財産的基礎を有していること、役員や個人事業主など経営上の重要な人物が一定の欠格要件に該当しないこと、適用事業所として社会保険および雇用保険に加入していることが必要です
建築業向けの管理システム「アイピア」
アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。
さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。
アイピアはここが便利!6つのポイント
工事管理の基礎に関する記事
工事管理システムに関する記事
- 【2024年最新版】工事管理システムとは?人気の20製品を機能付きで紹介!
- 施工管理システムを比較!導入するメリットや機能、選び方まで解説
- 【2024年最新】建築業(リフォーム・工務店向け)顧客管理システムとは?
- 工事原価管理システム厳選5選!メリットやありがちな失敗をご紹介