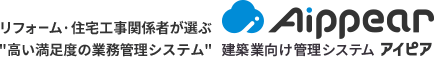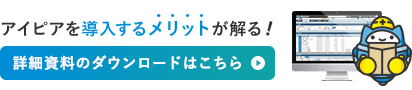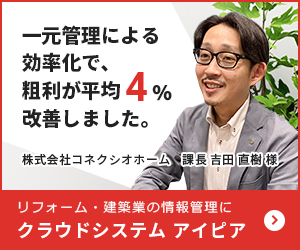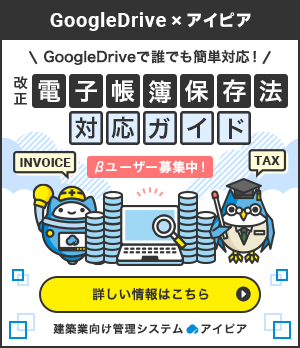リフォーム工事における課題の一つに、「原価管理が難しい」というものがあります。
御社でも、工事が完了し請求書が送付されてから原価の把握が難しく、粗利が低下していることに気づいたことはありませんか?
そのような場合には、様々な要因が考えられます。
まず、見積もり作成段階で原価を正確に計算できていない可能性があります。
また、工事中に予期せぬ補修やサービスの値引きが発生することもありますし、発注業務の状況が現場担当者しか把握していない場合も考えられます。
これらの問題を解決し、完工粗利の低下を防ぐためには、見積もり作成時に原価計算書を作成し、工事の進行に応じて原価管理を行うことが重要です。
そこで、今回は原価計算書作成のポイントとおすすめのシステムをご紹介します。
目次
原価計算書とは
原価計算書(または工事原価計算書)は、言葉の通り工事の原価を計算して記録するものです。
見積書と同じようなデザインで、各項目にどれくらい原価が掛かっているかを記録します。
この書類は、工事の各工程や材料、人件費、間接費などの費用を細かく分析し、進行状況や予算との整合性を確認するために利用されます。
また、工事の実施後には実績と見積もりとの比較も行われ、将来の工事計画や原価見積りに生かされることもあります。
このように、原価計算書は工事の透明性を高め、効率的な原価管理を支援する重要なツールとなっています。

原価管理について詳しくはこちら
原価計算書の作り方(ポイント)
では、実際に原価計算書を作成する方法と、ポイントをご紹介します。
見積書と一緒に原価を作成する
見積書作成の際に、同時に原価計算を行うことで、各項目の価格根拠を明確にすることができます。
この方法により、見積金額を算出する際には無根拠な値引きなどを排除し、粗利益の低下を防ぐことが可能です。

このように、項目一つ一つを作成する際に都度見積価格と原価を入力していきます。
ただし、これを行う場合、普段原価を入力する習慣がないと見積作成時間が2倍かかってしまう可能性があります。
効率を上げるためには、よく使われる項目に関しては標準単価表を作成するなどの取り組みが必要です。
標準単価表に関連する記事はこちら
合計金額や粗利をチェックしながら見積を作成する
原価を同時に作成する状態になったら、合計金額や粗利を確認しながら作業を進めましょう。
特に、粗利率を把握しながら見積もりを作成することで、利益を確保した見積もりを作成することができます。

例えば、この図の場合、粗利率は現時点で13.75%です。新たな見積項目を追加するかどうかに関わらず、このままでは提出しても利益がほとんど残りません。原価計算を同時に行うことで、このような情報を作成途中でも確認できるのです。
見積価格は原価を基準に計算されます。これまでの図では、「1.項目名」「2.見積金額」「3.原価」という順序で記載されていますが、実際に項目を作成する際には「1.項目名」「2.原価」「3.見積金額」という順序で作業を進めるのが望ましいです。原価を基準に金額を計算することで、見積書をより効果的に作成することができます。
「この工事は原価が〇〇円で、粗利は〇%確保したいので見積金額はこれくらい」
というロジックで見積書を作成していきましょう。
リフォーム会社が粗利率をアップさせるための具体的な手法と成功事例の記事はこちら
原価計算書を作成することのメリット
原価計算書の作り方が分かったところで、そのメリットについておさらいしましょう。
- 粗利率を確認しながら見積を作成することで、粗利率低下を抑えられる
- 価格の根拠が明確になる
- 標準粗利率を設定することで、無根拠な値引きなどがしづらくなる
- 標準単価表の作成のきっかけになり、業務改善が更に行える
- 原価が明確なので、発注フローがスムーズになる
その他に、もしお客様に価格の根拠提示を依頼された際にも、原価計算書を作っておくことで速やかな回答ができるうえに、信頼性を高めることもできます。
原価計算書を作れるようになったら(将来的なビジョン)
原価計算書の作成ができるようになれば、次のステップとして業務改善を進めることができます。
例えば、原価計算書を基に発注を行うことが挙げられます。原価計算した金額をもとに正確な発注ができるかどうか、工事が終了するまでの進捗が明確になります。これにより、完工時の粗利率低下を抑えることができます。
さらに、発注状況や工事の進捗状況をリアルタイムで把握することも可能になります。工事の追加や補修などが発生した場合も、原価計算情報を追記することで現時点での粗利率が把握できます。
粗利率をリアルタイムで把握することで、突発的な問題にも迅速に対応できるようになります。
原価管理ができる建築業・リフォーム業向け管理システム アイピア
アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。
さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。
アイピアはここが便利!6つのポイント
リフォーム業向け 原価管理ができるクラウドシステム 厳選3選
原価管理システム どっと原価NEO
『どっと原価NEO』は、建設業の原価管理を飛躍的に標準化・効率化させることができるシステムです。そのため、リフォーム会社でも利用可能です。原価管理を細かく管理し、粗利の向上を目指す企業に特におすすめです。
どっと原価NEO
- 自社に合わせた仕様にカスタマイズが可能
- 6階層まで対応した見積書の作成ができる
- 4階層まで対応した実行予算の作成ができる
- 原価集計が可能で様々な視点から分析が可能
| 環境 | クラウド型 |
|---|---|
| 機能 | 見積作成、原価発注管理、工程管理、顧客管理、営業進捗管理、請求管理、入金管理、帳票作成、現場日報管理、仕入伝票入力、原価配賦、労災保険料計算、勤怠連動 |
| 価格 | どっと原価3(ライト):月額利用料 13,000円~ どっと原価3(スタンダード):23,000円~ |
| 体験版 | 要問合せ |
レッツ原価管理Go2 クラウド
『レッツ原価管理GO 2』は、クラウド型の原価管理システムで、プロジェクトごとに利益管理が可能です。このシステムの特長は、使いやすさにあります。見積もりから発注、発注から仕入れといったデータの流れをスムーズに行えるリレー機能を備えているため、二重入力の手間を省くことができます。
レッツ原価管理Go2
- どの部門でも使える基幹システムの価値を提供
- リレー機能が搭載されており、二度打ち不用
- 導入検討から運用までレッツ独自の手厚いサポート
- 無料体験で購入までに「使える」を実現
| 環境 | スタンドアロン版、クラウド版 |
|---|---|
| 機能 | 見積作成、原価発注管理、工程管理、顧客管理、請求管理、入金管理、帳票作成、出面管理、在庫管理、立替仕入、支払査定、会計給与ソフト連携、サービス連携、アドオン、レッツドライブ |
| 価格 | スタンドアロン版:初期導入費:660,000円 年間保守:33,000円~ クラウド版:初期導入費:1,100,000円 年間保守:55,000円~ |
| 体験版 | 無料体験あり(45日間) |
SMILE V 2nd Edition コストマネージャー
SMILE コストマネージャーは、発注・予算・支払・請求をトータルでサポートするシステムです。
クラウド型の他に、オンプレミスでの提供も行っています。
特徴
- 多角的な原価分析ができる
- 要素細目別・作業工程分類別で実行予算の登録が可能
- 発生原価に発注残を含めた見込み原価が分かる
- 出来高管理や共通費配賦も可能
- IT導入補助金対象製品
| 環境 | クラウド版 |
|---|---|
| 機能 | 原価管理、発注・予算・請求、分析機能 |
| 価格 | 要問合せ |
| 体験版 | 要問合せ |
さらに詳しい原価管理システムについてはこちら
まとめ
今回は、見積作成時に原価計算書を作成する方法についてご紹介しました。ただし、これらの改善は、一人の担当者が単独で行うことは難しいものです。
課題を根本的に解決するためには、リフォーム工事の業務フローそのものを見直したり、Excelを使用した見積作成や管理から脱却する必要があります。
まずは、それらの課題を明確にするために、リフォーム会社向けの見積システムを検討することが重要です。
まずは、それらの課題を明確にするためにもリフォーム会社向けの見積システムを検討しましょう。
原価管理の基礎に関する記事
- 【建設業向け】原価管理とは?その目的とメリットを簡単にご紹介。
- 知っておきたい原価計算の基礎知識から計算方法まで詳しく解説!
- 原価管理をきちんと行うためのABC(活動基準原価計算)計算方法やメリットも解説
- 【リフォーム業界向け】原価計算書を作成して粗利率低下を防止