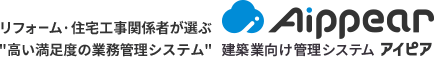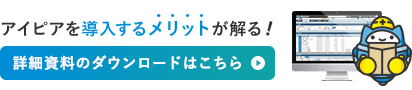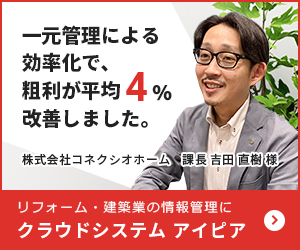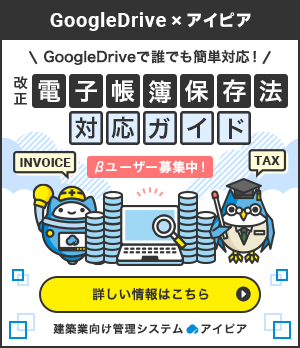近年、PM(プロジェクトマネジメント)業務やCM(コンストラクションマネジメント)業務を専門に提供するマネジメント会社やコストコンサルティング会社が急速に増えています。
これは建設プロジェクトの適正な管理方法が普及し、コスト面での透明性や効率性に社会の注目が集まるようになったからです。
この記事では、そもそもコストマネジメントとは何か、具体的にどのようなことを行うのか、またCM会社に依頼するメリットをご紹介します。
目次
コストマネジメントとは

コストマネジメントとは、開発事業における建設マネジメントのうちコスト管理を意味する言葉です。
プロジェクトの構想・企画段階から設計、発注、施工、工事後の維持・修繕、解体まで、建物のライフサイクル全体におけるコスト管理を指すこともあります。
建設プロジェクトでのコストマネジメントは範囲が広く、段階によって内容も異なります。
一貫してやるべきことは、発注者の要望に基づいて適正な予算を想定し、プロジェクトの中で一貫したコスト管理を実施し、コストが予算内で収まるように管理することです。
建築コスト管理士に関する記事はこちら
コストマネジメントの業務
ここからは、コストマネジメントの業務内容についてみていきましょう。
各段階における主な業務は以下の通りです。
構想・企画段階のコストマネジメント
構想・企画段階では、以下の業務をコストマネジメントとして行います。
- ベンチマーク調査
- 目標予算の設定
- 事業の妥当性・採算性の検討
ベンチマーク調査
参考となる類似案件を調べ、分析を行います。
これらをベンチマークとし、今後のプロセスにおいて指標・達成すべき基準として扱うことになります。
予算設定の際には、過去の類似案件における工事費から「㎡単価」や「坪単価」で概算する手法が一般的です。
目標予算の設定
建物の用途、仕様(グレード)、規模、地域などの情報をもとに、目標とする予算の設定を行います。
なお、事業全体の予算を出すため、工事費等のハードコストのみならず、設計・コンサルタント等のソフトコストも含めて計算する必要があります。
目標予算は、高すぎると予算内であっても市場相場より高価になってしまったり、反対に低すぎると適正なコスト管理にも関わらず予算超過してしまったりすることがあります。
相場と照らし合わせて適切な目標予算を設定することが重要です。

事業の妥当性・採算性の検討
事業の妥当性・採算性の検討も重要です。
調査や目標予算の結果などから、実現可能なのか、十分に採算のとれるものなのかを見極めます。
この開発事業における実現可能性、採算性の検討は、フィージビリティスタディとも呼ばれます。
初期費用はもちろん、事業期間内に建物の維持・運用で必要となるランニングコストを踏まえ、事業の実現可能性や妥当性、採算性について検討することが重要です。
計画段階のコストマネジメント
次に、具体的な工事計画をたてる段階でのコストマネジメントをみていきましょう。
主に以下の3つを行います。
- 概算工事費の算出
- コストプランの作成
- コストシミュレーション
- コストプランの作成
概算工事費の算出
概算での工事費の算出を行います。
「仮設」「躯体」「内部仕上」「外部仕上」「電力設備」「空調設備」などの項目に基づいて、ざっくりとどのくらいの工事費になるのかを算出し、把握することが目的です。
コストプランの作成
次に、コストプランを作成します。
コストプランは、最初に定めた目標予算と各段階で求めた工事費について確認・把握する為のマネジメントツールです。
目標予算との大きな乖離がある項目は、妥当な乖離であるのか、改善が可能なのかを確認・検討します。
コストプランは、全てのプロセスにおいて常に使用するものです。
コストシミュレーション
コストプランなどをもとに費用対効果を試算するシミュレーションも行います。
特に複数のプランがある場合には、比較検討も行うのが一般的です。
概算システムを用いて、どの案が最適かを考えます。
設計段階のコストマネジメント
施工に向けた設計段階でのコストマネジメントは、以下の通りです。
- 積算による工事費の算出
- 現状のコスト確認
- 設計VEの実施
- リスク要因の洗い出し・トラブル対応策の検討
- 現状のコスト確認
積算による工事費の算出
概算での工事費算出を参考にしながら、積算で工事費を算出します。
比較的限られた情報量でざっくりと求めるのが概算であるのに対し、積算は多くの情報をもとに手間をかけながら精度の高い計算をするものです。
現状のコスト確認
算出した工事費をコストプランに記入し、現状のコストが目標予算内に収まっているか確認をします。
工事費全体と工事項目ごとのそれぞれについて、予算との乖離がないかチェックします。
設計VEの実施
設計VE(バリューエンジニアリング)とは、設計内容を多面的にレビューして発注者の視点から費用対効果の向上を図る業務のことです。
設計VEの目的は、発注者が求める建物の機能とコストならびにスケジュールの観点から費用対効果の向上を図ることにあります。
設計VEは、設計者とは異なる者によって行われるものです。
設計図とコストに無駄や過剰な部分がないか確認するだけでなく、改善代案を模索し「VE提案」として提示します。
リスク要因の洗い出し・対応策の検討
工事には、不慮の事態がつきものです。
さまざまなリスク要因が考えられるため、考えうるリスク要因を事前に洗い出します。
そのうえで、それぞれの対応策を考えておくと、いざトラブルが起こった際にも対応しやすくなるでしょう。
工事発注段階のコストマネジメント
次に、工事を発注する際のコストマネジメントについてです。
- 発注方式と契約方式の検討
- 入札書類の作成
- 見積書の精査・評価と業者の選定
- 契約条件・価格の交渉
- 入札書類の作成
発注方式と契約方式の検討
どのような発注や契約の方式が最適かを検討します。
建設プロジェクトは個別に異なる特徴を備えており個別性が高いので、プロジェクトの詳細な状況を把握することが重要です。
大きくは「発注者」「建設会社」「建設市場」といった3つの観点よりプロジェクトの目的や置かれている状況を客観的に捉えて検討を進めます。
入札書類の作成
発注の際に必要な書類を作成します。
例えば、以下のようなものが挙げられます。
- 見積要項書
- 仕様書
- 特記仕様書
- 見積作成要項書
- 見積内訳書式
- 参考数量書
- 質疑書
見積書の精査・評価と業者の選定
入札を実施する際には、施工業者の洗い出し、見積の声掛け、説明会実施、見積書徴収、質疑応答、交渉など、あらゆる調整業務を行います。
施工業者から見積書が提示されたら、内容に漏れがないか、不明な点がないかを確認します。
その後、価格や実績、技術力などをもとに総合的に判断し、発注する業者を選定しましょう。
契約条件・価格の交渉
業者の選定が完了したら、実際に契約を締結するための、契約条件・価格の交渉を行う段階です。
複数業者に交渉を行うこともあれば、1社のみ選定して行われることもあります。
施工段階のコストマネジメント
施工段階においても、コストマネジメントが重要です。
具体的な内容をみていきましょう。
- 変更コストの管理
- コストモニタリング
- 出来高査定と最終工事費の清算
- コストモニタリング
変更コストの管理
施工段階において、設計変更がなされることはしばしばあるものです。
そのため、変更工事に伴うコスト管理が非常に重要になってきます。
変更工事が認められるかどうか(工事契約書を踏まえて)の協議、変更コストの合意、工事管理シートでの変更コスト管理などを行います。
コストモニタリング
現状のコストを目標予算と照らし合わせてモニタリングする作業も重要です。
目標予算からの増減を求め、発注者や施工者に報告します。
出来高査定と最終工事費の清算
工事契約書の支払い条件にもとづいたタイミングで、出来高査定を行い、竣工後に最終工事費の清算が行われます。
変更工事があった場合には、変更工事管理の記録を踏まえて、協議のもと最終工事費とまとめて清算されるのが一般的です。
CM会社のコストマネジメントのメリット

CM(コンストラクションマネジメント)会社にコストマネジメントを依頼するメリットについて、ご紹介します。
発注者のサポート
CM会社は、発注者・施工者から独立した立場で、発注者に対して的確なサポートを行います。
例えば、発注者側のチームの課題や企画実現に向けた課題を洗い出し、チームの弱点を補うサポートが可能です。
洗い出した課題は、専門知識を活かして、その場に応じた対応で課題を解決していきます。
適正なスケジュールや予算の設定
CM会社ならではの多くのプロジェクトを支えた経験と膨大なデータから、市場動向も含めた的確な目標設定が可能です。
特にスケジュールの設定に関しては、類似案件を基にした具体的なデータから、工期の延伸も視野に入れた柔軟なスケジュールの設定ができます。
費用対効果の高いプラン提示
発注者の意向を踏まえた客観的な視点から、計画や設計の内容を見直し、より費用対効果の高い案を提案し、発注者が納得する形で提示します。
大枠をそのままに少し見直すだけで、コストの削減・工期の短縮といった、具体性のある代替案を提示することも可能です。
発注におけるコスト・手間の削減
近年、建設市場では工事の発注方式がより複雑になり多様化しています。
CM会社は発注における方式・業者の選定も行うため、多角的に比較検討した上で、発注者に取って最適な発注方式を選んで発注してもらうことができます。
その際に、候補会社とのやり取りを一本化して、窓口をCM会社に任せることも可能です。
発注者が候補者と直接やりとりする必要がなくなるので、大幅に時間の節約ができるでしょう。
また、見積書の内容を過去のデータや市場の状況に基づいて精査できることから、根拠や説得力のある価格交渉でコストダウンが期待できます。
プロジェクト管理に関する記事はこちら
CM会社の選び方のポイント

ここからは、CM会社を選ぶ際のポイントについてみていきましょう。
CM会社選定の流れ
一般的なCM会社への依頼の流れは、以下の画像の通りです。
まず、発注者が要件を整理し、RFP(提案依頼書)を作成します。
RFPをもとに複数社に提案を依頼した後、候補会社から業務提案書が提出されます。
業務提案書の内容が発注者の求める条件を満たしているかを審査した上で、プレゼンやインタビューなどの評価も加え、1社に絞り込む流れとなります。
RFP(提案依頼書)の書き方
RFPとはRequest For Proposalの略で、提案依頼書とも呼ばれます。
発注者や建設プロジェクトの基本情報、要件などを記載する書類です。
RFPには、どのようなプロジェクトなのかがわかるよう、以下の情報を記載します。
- 依頼の背景・目的:CM業務が必要な背景と目的
- 建設プロジェクト概要:案件所在地、用途、規模、構造、スケジュールなど
- 建設プロジェクトのステータス:「企画中」や「計画段階」などプロジェクトの現状や体制
- 依頼したい業務の範囲・要件:依頼したい業務の具体的な内容、成果物等の要件
- 選定について:スケジュール、提案書の提出期限、プレゼン日程、質疑方法、重視する点等
- 担当者の情報:所在地、連絡先等
候補会社の選定
選定の対象となる候補会社の決定も重要なポイントです。
プロジェクトの内容にも寄りますが、4~6社程度を候補とすることが多いです。
選定の際は、以下の点を確認するようにしましょう。
- 会社の基本情報(規模、所在地等)
- 業務内容が分かりやすく説明されているか
- 類似案件のCM業務実績があるか
- 競合他社がクライアントにいるか
業務提案書の評価のポイント
候補会社から業務提案書が提出されたら、その内容を精査し、評価します。
業務提案書には、以下の内容を書いてもらうことが多いです。
- 提案概要:業務提案の概要
- 実施方針:具体的な実施方針の提案
- スケジュール:プロジェクト全体スケジュールを踏まえた業務実施スケジュール
- 実施体制:業務責任者、主担当者、担当技術者などの実施体制
- 類似業務実績:会社、業務責任者、主担当者の類似業務における実績・経験
- 業務費:提案内容に基づいた業務費
- その他:セキュリティ体制、範囲外業務、制約事項など
提出された業務提案書では、特に以下のポイントを確認するようにしましょう。
- プロジェクトの目的と課題への理解
- 課題に対する具体的な提案
- 提案内容の分かりやすさ
- 他社とは違う評価対象があるか(実績など)
- 実施スケジュールの具体性
- 各担当者の具体的な役割の提示
業務費そのものはここでは重視しないのがおすすめです。
最終的な業務内容によって業務費は大きく変わり得る点、異なる提案内容での比較は難しい点などが理由として挙げられます。
プレゼンテーション
プレゼンテーションは、その後も頻繁にやり取りを重ねることから主任担当者に担当してもらうのが理想的です。
インタビューでは、窓口となる主任担当者の説明や表現方法が、分かりやすいかどうかをよく確認しましょう。
インタビューのポイント
インタビューは、業務提案について、さまざまな角度から深掘りをする機会です。
主には、主任担当者と担当技術者の経験や実績を判断します。
主任担当者は調整・マネジメント能力、担当技術者は技術的な能力・経験が十分かどうかを聞き出します。
直近の類似案件でプロジェクトに取り組んだ経験の有無を確認し、経験がある場合は具体的に成果の聞き取りをします。
最終的には、その担当者や技術者の人となりもあり、意見や要望を言いやすい人を選ぶのも一つの方法です。
施工管理に関する記事はこちら
コストマネジメントの業務費

CM会社に業務を依頼する場合の費用相場は、ほとんどが人件費となるので、同じプロジェクトであっても「業務期間」「業務内容」「実施方針や実施体制」により大きく変動します。
概算する方法は大きく分けて2種類あります。
工事費に対する割合で計算する方法
【概算CM業務費の計算式①】
工事費(億円)×CM業務費率(%)= 概算CM業務費(円)
この計算式は費用の目安を簡単に把握できますが、概算の精度については多少粗くなります。
業務期間と担当者数から計算する方法
【概算CM業務費の計算式②】
業務期間(カ月)× 担当者数(人)× 単価(円/人・月)= 概算CM業務費(円)
この計算式は、プロジェクトで必要なCM業務を業務期間や担当者数を想定して概算する方法です。
前述した工事費と業務費率から概算する方法より手間がかかるのですが、より高い精度で概算費用を得ることができます。
CM業務費を決定する方法
尚、発注者とCM会社との間で、費用を取り決める代表的な方法は下記の通りです。
【CM業務費の計算式①】業務工数の積み上げによる方法
直接人件費(円)+ 諸経費等(円)+ その他(円)= CM業務費(円)
【CM業務費の計算式②】成果報酬による方法
基本業務費(円)+ 成果報酬(円)= CM業務費(円)
工事費に関する記事はこちら
原価管理ができる!『建築・リフォーム業向け管理システム アイピア』
アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。
さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。
アイピアはここが便利!6つのポイント
まとめ
コストマネジメントとは、建設プロジェクトにおけるマネジメント業務の一種で、企画から施工、施工後までのコスト管理を行うことです。
近年、CM(コンストラクションマネジメント)会社と呼ばれる、建設マネジメントの専門会社にコストマネジメントを依頼することが増えています。
CM会社に依頼するメリットは、ノウハウを生かした目標・スケジュール設定、費用対効果の向上、発注の手間の削減、など多くあります。
ご紹介した選定のポイントを参考に、自社に合うCM会社を探してみてはいかがでしょうか。
原価管理の基礎に関する記事
- 【建設業向け】原価管理とは?その目的とメリットを簡単にご紹介。
- 知っておきたい原価計算の基礎知識から計算方法まで詳しく解説!
- 原価管理をきちんと行うためのABC(活動基準原価計算)計算方法やメリットも解説
- 【リフォーム業界向け】原価計算書を作成して粗利率低下を防止