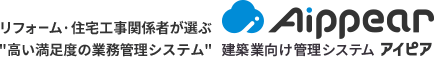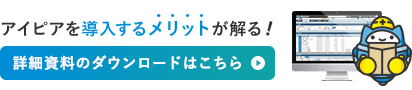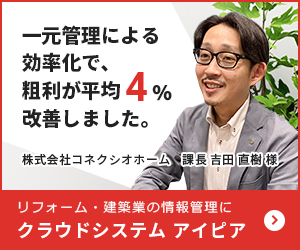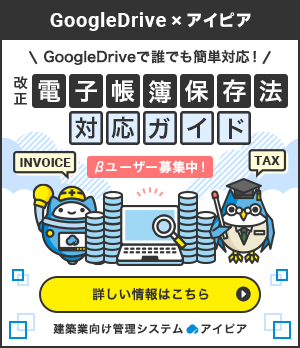時間削減・利益UP・情報共有ができる
IT導入補助金でお得に導入!
業務効率化ならアイピア
アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、工事の情報を一括で管理できるため情報共有の手間が削減されます。さらにアイピアはクラウドシステム。外出先からでもデータを確認できます。
業務効率化は、現代社会において、企業が抱える大きな課題の一つです。
必要だとわかっていてもなかなか本格的に取り組めない、ということも多いのではないでしょうか。
ここでは、業務効率化について理解を深め、業務効率化のアイデアや進め方、進める際のポイントなどをわかりやすくご紹介します。
業務効率化とは

業務効率化とは、業務における「ムリ、ムダ、ムラ」をなくし、業務を効率的に進めることを目指す取り組みのことです。
日頃気づかないうちに、業務のなかにはあらゆる「ムリ、ムダ、ムラ」が生じています。
これらを発見し、見直し、改善することが、業務効率化の中身です。
業務効率化が必要な理由
そもそも、業務効率化はなぜ必要とされているのでしょうか。
労働人口の減少のため
日本では、少子高齢化による労働人口の減少が避けられない状況です。
また、この人口減少に伴う国内需要の減少、グローバル化による競争相手の拡大などが今後顕著になると予想されます。
その為、今後はより少人数・短時間で効率的に業務をこなしていくことが、あらゆる企業で求められていくことになります。
「働き方改革」推進のため
昨今では、ワークライフバランスを求める動きが高まり、残業や休日出勤を減らそう、なくそうという考えが強まっています。
また、政府主導の「働き方改革」も進められているところです。
これまで当たり前のように残業をしていた日本の企業風土の中では「限られた時間の中でいかに効率よく業務をこなすか」という視点は、欠けていた部分かもしれません。
働き方のニーズの多様化、働き方改革の推進に企業も対応していく必要があります。
働き方改革に関する記事はこちら
業務効率化のメリット

業務効率化は、多くのメリットを企業にもたらします。
具体的なメリットをみていきましょう。
コストの削減
「ムリ・ムダ・ムラ」を省くことで作業時間の削減に繋がり、残業や休日出勤等の人件費、光熱費等の経費削減が可能になります。
コスト削減の結果として、利益率や生産性をアップさせることができるでしょう。
働きやすい環境の実現
労働時間の短縮(残業時間や休日出勤の軽減)や待遇の向上によって、働きやすい環境を実現できれば、以下のような多くの効果が企業にもたらされます。
- 従業員の健康維持・モチベーション向上
- 働き方改革への対応
- 離職の防止
- 優秀な人材確保
従業員の健康維持や能力アップに繋がり、集中力やモチベーションの向上が期待できるでしょう。
また、働き方改革に対応できるようになるほか、離職の防止や優秀な人材の確保にも繋がり、総合的に人材リソースを増加させることができます。
事業の発展
業務効率化によって生み出された時間・資金を使って、これまで注力できなかった業務や新しい取り組みを行うことができるようになります。
- 組織改革・マネジメントの強化
- 新規事業への進出
例えば、組織改革やマネジメントの強化が挙げられます。
また、削減できた時間や資金を新規事業に投資しやすくなるため、新規事業への進出も考えられるでしょう。
業務改革・業務改善に関する記事はこちら
業務効率化のアイデア

ここでは、業務効率化の具体例をご紹介いたします。
業務効率化を実践する際は、これらの例をぜひ参考にしてください。
ITツール・システムの活用
業務効率化の一つとしてITツールやシステムを活用する方法があります。
業務管理システム
業務の効率化には、それぞれの業務に特化した業務管理システムの導入がおすすめです。
- 経理・会計システム
- 営業支援ツール
- 勤怠管理システム
- 給与計算システム
など、様々な業務管理システムが提供されているので、自社の効率化したい業務に合ったシステムがないか、調べてみましょう。
コミュニケーション・情報共有ツール
ビジネスチャットやウェブ会議ツールに代表されるような、コミュニケーション・情報共有を効率化できるツールもあります。
メールなどと比較して速さと手軽さが特徴で、今までやりとりしたメッセージがクラウド上で参照できるため、情報共有の手間が削減できるのがメリットです。
チャット機能があれば会話のようにメッセージを送り合えるため、社内のコミュニケーションが円滑になります。
複数名でのメッセージの送受信やファイルの共有も可能です。
自動化・システム化
業務のなかに繰り返し行う作業や単純作業があれば、エクセルやRPAツールのようなシステムを用いて自動化を図ることがおすすめです。
自動化を行うことで、作業効率がアップするほか、人の手で行うよりもミスが起こりにくくなります。
外部リソースの活用
コストを下げつつより良い業務を行うには、外部リソースを活用することもおすすめです。
専門家のコンサルティングを受ける・専門家の意見を聞く
コンサルタントは、ある事柄についての専門家であり、個人や企業に助言する立場の人のことを言います。
専門家によるコンサルティングサービスを利用して、自社の課題を解決し、業務効率化を図ることができます。
業務をアウトソーシングする
アウトソーシングは、自社の業務の一部、またはすべてを外部に委託して業務の効率化を図る方法です。
社内の専門知識やスキルが不足している場合などに、アウトソーシング先の専門技術を積極的に活用するという方法があります。
時間短縮の工夫をする
時間短縮の工夫を重ねるという、低コストで簡単に業務効率化を進める方法もあります。
時間短縮のテクニックとして、例えば以下のようなものが挙げられます。
- よく使う書式・データはテンプレート化する
- ショートカットキーを利用する
- 社内でよく使う単語はパソコンに単語登録する
- 主要業務のコアタイム(集中してその業務に取り組む時間)を定める
一つ一つは非常に細かいことですが、積み重なると相当の時間節約が可能です。
環境・備品の整備
環境・備品の整備もまた、業務効率化に繋がることがあります。
例えば、備品の収納場所やオフィスのレイアウトを、業務フローに合う形へ変えることで、作業動線が悪く移動が面倒、備品を取り出しにくい等の問題が解決され、従業員が働きやすくなります。
また、スペックの高いPCを導入したり、使いやすい機種を選んだりすることや、反対に不要と思われるものを捨てるといったことも、業務効率化に繋がる手段です。
業務フロー、業務構造の改善
業務の取り組み方のみならず、業務フローや業務構造そのものを改善することは、業務効率化を進める重要な手段と言えるでしょう。
なんとなく習慣化している業務プロセスのなかにも、実は効率化できるものが潜んでいるかもしれません。
日頃の業務内容を可視化して、不要なプロセスは改善・廃止しましょう。
会議時間の短縮化・不要な会議の廃止
長時間行われがちな会議について、本当に必要なのかを再検討するのも手です。
参加人数を絞る、会議資料の事前共有、会議の目的の明確化、会議議事録の作成・共有、会議時間をあらかじめ決めておく等の対策で会議時間の短縮化を図りましょう。
また、「そもそもその会議が本当に必要なのか」を考え、不要であれば回数を減らしたり廃止したりするのも策だと思います。
その分、資料作成など会議の準備に費やす工数を節約でき、出席予定者は空いた時間を他の業務に充てることが出来ます。
情報共有の促進
情報共有の促進も、業務効率化を進める手段の一つです。
社内での情報共有がスムーズになるだけで、承認ワークフローが迅速に進む、ノウハウが蓄積されるなど業務効率化の点で多くのメリットがあります。
社内でのコミュニケーション機会を設ける、先述した情報共有ツールを導入するなどして、社内の情報共有を活性化しましょう。
業務のルール化・標準化
業務のルールを定める、業務内容やアウトプット水準を整理し社内で業務標準化するといった方法もあります。
人によって業務内容が大きく異なっていると、情報共有の手間がかかったり、生産性や成果物の質が不均一になったりします。
業務内容を統一し明確化し、社内でしっかりと共有することで、ムラをなくすことが可能です。
業務マニュアルの作成
業務マニュアルを作成することで、業務の内容や進め方を明らかにすることができます。
マニュアルがあることにより、業務の均一化による品質の向上、不要な手順や業務の発見などの効果が期待できるでしょう。
社内で使う書式の統一
社内で使う文章の作成に使うソフトをそろえ、フォーマットを統一する方法です。
書式の統一ができるので、部署ごとに書式を変更する必要がなくなるほか、他の部署が書類確認する際、同じ書式であれば、確認作業もスムーズになります。
業務標準化・マニュアル作成に関する記事はこちら
業務効率化の進め方・進める際のポイント

この章では、業務効率化の進め方、進める際のポイントをご紹介します。
①現状把握・改善すべき業務の選定
業務内容について、タスク内容、担当部署、かかる時間、頻度などを書き出し、現状を把握します。
従業員や担当スタッフからヒアリングをしながら行うと進めやすいです。
現状把握を行うことで、非効率な業務やムダな作業などの問題点が明確となります。
その中から、改善すべき業務を選定します。
ポイント1
効率化しやすい業務を見極める
一度にすべての業務を効率化することは難しいため、効率化しやすい業務を見極めるようにしましょう。
例えば、高度な判断が求められず難易度が低い業務は、ツールやシステム導入で効率化しやすいです。
また、定型化が図りやすい、発生頻度が多い、マニュアル化しやすいといった業務から着手するのもおすすめです。
ポイント2
問題ごとの関連性に注目する
一見別の問題でも、実は関連している、といったこともあります。
問題を見つめるときは、問題ごとの関連性に注目して、何が根本的な原因なのかを明確にすると良いでしょう。
ポイント3
具体的な目標をたてる
改善する問題を明確化すると同時に、評価しやすい、具体的な目標をたて、改善度合いが見えるようにするようにしましょう。
「1か月で残業時間が1人当たり○○時間減る」や「〇か月以内に1回の会議時間が〇分以内におさまるようになる」など、評価しやすい具体的な目標をたてると、業務効率化の効果が見えやすく、社内全体に周知しやすくなります。
②問題の解決策の検討・決定と実施
改善すべき業務が決定したら、解決策を検討します。
先ほどご紹介した業務効率化のアイデアを参考に、改善すべき業務にあった解決策を検討・決定しましょう。
また、「改善の4原則」とも呼ばれるフレームワーク、「ECRS(イクルス)」を念頭に入れて行うと決定しやすいです。

ポイント4
手段と目的を分けて考える
手段と目的をしっかりと分けて考えることが大切です。
例えば、文書を探すことに手間取り、業務時間が長くなっていた場合、解決策は、文書のファイリングや電子化となります。
この時、文章のファイリングや電子化は、あくまでも手段であり、目的ではありません。
ファイリングや電子化の実現に注力することでかえって業務時間が増えては意味がないので、あくまで「業務時間の短縮」が目的であることを忘れないようにしましょう。
③改善の実施・実施後の評価
解決策が決まったら、計画をもとに解決策を実施します。
実施した後は、計画に沿ってどれだけ進められたか、どれほどの改善が出来たかを、設定した目標をもとに評価しましょう。
社員に改善策の実施後、どのような変化があったのかヒアリングすることも重要です。
社員の意見から、次に取り組むべき新しい問題点に気づくことができ、さらなる業務効率化のヒントが見えてくることでしょう。
ポイント5
計画は柔軟に変更する
いざ実施してみて上手くいかないことは、継続せず、柔軟に変えてみることも大切です。
定期的に進捗や効果を確認し、上手くいかなければ適宜内容を変更しましょう。
ポイント6
従業員への配慮を忘れずに行う
業務効率化によって最も影響を受けるのは、業務を担当する従業員です。
「なぜ業務効率化が必要なのか」はもちろん、改善後の業務を定着しやすくするためや変更による従業員の負担を軽減するための取り組みも忘れずに行いましょう。
ポイント7
結果を社内で共有する
業務効率化の評価と考察は、社内で共有することが大切です。
良かった点も悪かった点も含め、すべての評価・考察を社内で共有することで、様々な意見が得られたり、その後も同じ目標に向かって進んでいきやすくなります。
建築業における業務効率化に関する記事はこちら
業務効率化なら『建築業向け管理システム アイピア』
アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。
さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。
アイピアはここが便利!6つのポイント
まとめ
業務効率化とは、業務をより効率的に進めるための取り組みを指します。
ムリ、ムラ、ムダをなくすことが業務効率化の基本です。
業務効率化では、自社の現状や抱える問題を把握・分析し、どんな手順・方法を用いれば最適かを、十分に検討して選択することが大切です。
様々な具体策の中から自社に合ったものを取り入れて、業務効率化を図りましょう。
kyozonは、法人向けクラウドサービス・SaaS・IT製品の比較・資料請求サイトです。
SaaSの比較や検索、デジタルトレンドの最新情報などをお届けし、日々の業務をスマートにする最適なSaaSやITツール選びをコンシェルジュのようにご支援させていただきます。
SaaS・ITサービスの比較サイトならkyozon
業務改善を進めるポイントはこちら
- 業務改善を効率的に進めるポイントとは?
- 【工務店の業務改善】施工管理の効率化方法と効率化のメリットとは
- 【超初級】業務改善報告書の基本的な書き方とは?テンプレート例つき
- 【最新版】業務改善助成金とは?簡単な申請方法から注意点まで
- 業務効率化とは?具体策と進める際のポイントを解説
- 何から始めるべき?業務効率化で仕事の質を高めよう